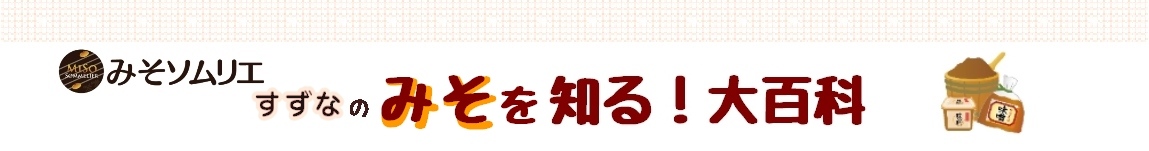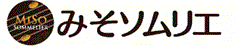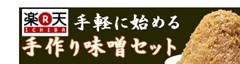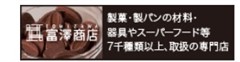江戸甘みそ
|
東京都 |
江戸甘味噌は東京都味噌工業協同組合の地域団体登録商標です。
江戸甘みその特徴
赤褐色の米みそです。
大豆は茹でずに蒸したものを用いるため、色が濃くなっています。
塩加減、甘さ加減が京都の白みそと同じで、仙台みそや信州みそといった普通の辛みそと比べると、麹は2倍、塩は半分です。
米麹をたっぷり使用しているため庶民向けというより高級品でした。砂糖類は入っていないのにこれほどの甘さか、と思えるほど濃厚な甘味があり、ねっとりとした感触。そのままなめみそとしても、また和菓子にも使えるのではと思えます。
熟成期間は短く10日間程度。
塩分が少ないので変質が早く、夏季には10日程しか保存できません。そのため、江戸の外から持ち込むのではなく、江戸市中のみそ蔵に製造が限られました。
みそ田楽、どじょう汁といった江戸(東京)の料理に巧みに使われ人気を博しました。
江戸甘みその歴史

1603年(慶長8年)江戸に幕府が開かれたことで江戸は劇的に人口が増加しました。
人口百万人を超えたのが早くも元禄期(1688〜1699年)です。
開幕当時、みそは「買いみそは恥」という風潮もあって商売になりにくい品物でしたが、人口が増えるとともに京都の白みそや三河の豆みそ、仙台みそ、田舎みそなど、特に上方からは 下りもの として大量のみそが江戸の台所を賄いました。
一方、江戸独自のみそがつくられるようになりました。
江戸のみそ醸造家に伝わる話では、初代将軍徳川家康(1542〜1616)の命により、出身地三河の八丁みそ の旨みと、京都 白みその甘さを兼ね備えたみそとして開発されたそうです。

京・大阪の甘い味が下りものとして珍重され、甘口のみそが好まれ江戸のみそも甘みそとなりました。
人口百万人の江戸の食を支えるために江戸でもみそ蔵、すなわち工場での量販体制が整えられていきます。
関東ローム層を利用し、本郷の麹屋が始めたみそ醸造家が工場生産のさきがけと考えられています。
江戸の狭い土地では、みそ醸造もあくまでも小規模で、1651年(嘉永4年)には江戸のみそ問屋140軒のうち半数は本郷に集中(『日本食生活表』西東秋男著)していたとあります。
また、江戸甘みそは醸造期間が短いので、大がかりな設備も必要としなかったことも江戸の土地事情と適合したようです。
江戸時代〜大正期が江戸甘みその最盛期で、河竹黙阿弥による歌舞伎『四千両小判梅葉』の台詞に使われたり、関東大震災で被災しつつも江戸のみそ醸造家は復興を遂げ、戦前までは東京の需要の過半数を占めていました。
『四千両小判梅葉』はこちら。

しかし、第二次大戦の最中に多量の米を使用する醸造法が政府から贅沢品に指定されたため、製造ができなくなってしまいます。
1951年(昭和26)年7月には統制も解除され、みそ製造も完全に自由になりましたが、この空白の10年で食生活の変化と嗜好の移り変わりで江戸甘みそは流通量が減ってしまいました。
平成15年に東京都より地域特産品の認定を受けています。
江戸甘みその製造元 製造メーカー