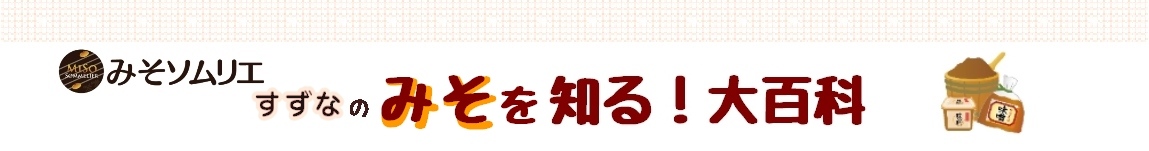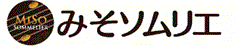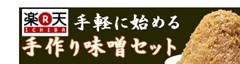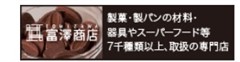仙台みそ
仙台みその歴史

1593年(文禄2年)の豊臣秀吉による朝鮮出兵に際し伊達政宗は朝鮮に渡って蔚山(うるさん)で戦いました。
その際、他藩のみそは夏場に腐敗してしまったのに、仙台藩のみそは変質せず味も優れていたことから、請われて他の武将に分ち与えたことから一躍仙台味噌の名を上げたと伝えられています。
しかしながら仙台という地名は1600年(慶長5年)に伊達政宗が名づけたとされるのでこの言い伝えは歴史的には不詳です。
1601年(慶長6年)仙台城に移り住んだ伊達政宗は、城下の老舗商人19人のひとり真壁屋 市兵衛に筆頭を命じ、「御用味噌」の看板を許可し「御用味噌屋」となりました。
真壁屋 市兵衛が1626年(寛永3年)に仙台味噌の招牌を掲げたのが元祖とされています。

戦国武将たちにとって戦闘能力を左右する兵糧。特に米とみそは絶対に必要な兵糧でしたので、政宗公は常に城中の糧とする目的で大規模なみそ醸造の設備御塩噌蔵(おえんそぐら)をつくり、真壁屋がその醸造・運営に当たりました。
この御塩噌蔵が最初のみそ工場といわれています。
一方、仙台藩の江戸藩邸に常勤する士卒 3,000人の食糧はすべて仙台から、みそは城内の御塩噌蔵から運ばれていました。
ニ代藩主忠宗の頃より、江戸大井の下屋敷(現在の品川区東大井4丁目の旧仙台坂付近)にみそ蔵がつくられ、国許からの大豆・米で御塩噌蔵と同様の醸造方法によりみそが仕込まれるようになりました。
下屋敷でのみその剰余分が江戸のみそ問屋へ払い下げられるようになったことから、江戸市中に仙台味噌の名が知られるようになり、大井の仙台藩下屋敷は「味噌屋敷」とも呼ばれるようになりました。
明治期においては、1872年(明治5年)に仙台藩下屋敷のみそ醸造所の経営を引き継いだ佐藤素拙(仙台下級藩士出身)によって、仙台みその醸造・販売が積極的に行われ、またその製法が東京府内のみそ醸造業者に広まり、多くのみそ屋が仙台みそをつくるようになりました。
仙台みそが東京の食卓を席巻したのです。

明治時代の末期になると、日本陸軍糧秣廠に勤めていた河村五郎(奈良県出身・東京の日出味噌創業者)が、麹の働きを温度管理で調節する味噌速醸法を考案し、醸造時間を年単位から数ヶ月に短縮することが可能になりました。
この醸造法は、後に特許が開放され、仙台みその醸造法とともに全国に普及したことから、他地域にも広まっていきました。
みそを使った宮城県の郷土料理 ご当地料理
- 牡蠣汁
- エゾアイナメのドンコ汁
- 松葉汁
- おろし汁
- 身欠きにしんのみそ漬け
仙台みその製造元 製造メーカー
- 玉松味噌醤油 株式会社
- 株式会社 山形屋商店
- 株式会社 高砂長寿味噌本舗
- 鎌田醤油 株式会社
- 川敬醸造 株式会社
- 有限会社 今野醸造
- 合資会社 海老喜商店
- ヤマカノ醸造 株式会社
- 株式会社 平野本店
- 株式会社 徳田屋