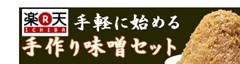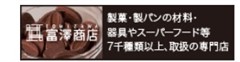みその起源
紀元前8世紀頃の古代中国、周王朝の『周礼(しゅらい)』という文献に醤(しょう)という字がみられ、この醤がみその起源といわれています。

醤は現代でも中華料理の調味料「ジャン」につながるもので、中国の伝統的な発酵食品です。獣肉や魚肉、果実や海藻、穀物をつぶし、塩と酒(麹)を混ぜて壺に漬け込み発酵させ、100日以上熟成させたものです。
中国語では醤を jiang と発音します。
また紀元前1世紀頃になると、大豆や雑穀を発酵させた豆支(し 豆へんに支)がつくられるようになりました。
日本でのみその伝わり方
日本へはどのように伝わったのでしょうか。
実は日本に伝来した年代は、はっきりとはわかっていません。
ただ縄文時代(〜BC4c)後期遺跡〜弥生時代(〜AD3c)中期にかけての住居跡から「醤」と同様のものが発掘されています。獣肉・魚・貝類をはじめとする食材が、塩蔵と自然発酵によって醤と同じような状態の遺物が残っていました。
飛鳥時代
藤原京(694年〜710年)跡から木簡が発掘され、「末醤」の字が確認されています。
諸国から献上された馬の飼育や調教にあたった馬寮(めりょう/うまのつかさ)という役所から、食品担当の官司に醤と末醤を請求した木簡で、表に「謹啓今忽有用処故醤」、裏には「及末醤欲給恐々謹請 馬寮」。
この段階では末醤です。粉末の醤ですから突いて粉(粒状)にした醤ということです。
奈良時代

醤や「豆支」(し)の文字が初めて文献にみられるのは701年(大宝1年)発布の大宝律令です。
大宝律令には天皇の食事を掌る役所名が書かれていますが、天皇の食事を掌る内膳司(ないぜんし)と、饗膳の食事を掌る大膳職(だいぜんしき/おおかしわでのつかさ)がありました。この大膳職は副食や調味料などの調達・製造・調理といった担当をしたのですが、大膳職に主醤(ひしおのつかさ)いう役職があると記されています。
さらに757年(天平宝字元年)に施行された養老律令では、大膳職の仕事として、肉や魚を塩辛状にした醢(ししびしお)、醤・未醤などの調味料、菓(くだものや雑穀餅)などを供給すると書かれており、大膳職が製造した醤や未醤を保管する別館施設として醤院(しょういん)と記されています。
史料『養老令』での主醤、未醤、醤院の記載はこちら。

1988年(昭和63年)〜1989年(平成元年)にかけて平城京の貴族邸宅跡(現在の奈良市二条大路南)から約4万点も発見された木簡に醤の字がありました。木簡は711年(和同4年)から716年(霊亀2年)のものとみられていますが、「急ぎの要で醤1合がほしい」と書かれています。ここでは調味料としてではなく薬として必要だったようです。
なおこの貴族低跡は奈良時代初頭の有力皇族 長屋王の邸宅跡と判明しています。
ことわざの「みそをつける」。失敗したとき、しくじったときのことをいいますが、火傷の治療にみそをつけて治したという伝承からきています。
古代中国の医療では醤をつけて傷を治す治療法があり、平安時代でもそれが伝わっていたからでしょうか。味噌は火傷にきくという伝承がことわざにもなっているのですね。
朝廷や貴族のあいだでの記録しかありませんが、製造・管理する役職まで定められていた…。かなりの高級品だったことがうかがわれます。
みその発展
平安時代

927年(延長5年)に完成した「延喜式」によると、当時の高級官僚には糯米やみそが月給として支給されていました。
延喜式には醤の醸造例が記され、醤は大豆、もち米、小麦、酒、塩を原料として発酵させた液体状の調味料です。醤油のはじまりといわれています。醤油の歴史として延喜式が取り上げられるのもこれによると思われます。
未醤は大豆、米、小麦、酒、塩を原料とした固体状のもので、みその祖先と考えられます。
また延喜式には「京の東市に醤を売る店51軒、西市に未醤を売る店32軒」との旨の記述もあります。この公設市場には、みそのほか米、塩、油、干魚といった食料品と、絹、綿、櫛、針、筆などの店がありました。
いずれも生活必需品です。みそはまだぜいたく品でしたが、生活に欠かせないものになりつつあったと思われます。
史料『延喜式』はこちらをご確認ください。
『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』は934年頃(平安時代中期)に作られた当時の辞書ですが、鎌倉時代中期の『塵袋(ちりぶくろ)』(1264〜1287年頃)という辞書と同様、末醤、未醤、が、その後味醤、味曽、味噌と変化していったものであると書かれています。
また『倭名類聚抄』には末醤、美蘇の産地として、滋賀、飛騨の名が載っています。
史料『倭名類聚抄』はこちら。
『塵袋』はこちらでご確認ください。
鎌倉時代

みその広がりにも禅宗の影響があります。
中国 宋から帰国した禅僧の影響ですり鉢が使われるようになり、すり鉢を使って粒みそをすりつぶした「すりみそ」がつくられるようになります。すりみそは水に溶けやすいので汁ものに使われるようになり、みそ汁が調理されるようになったのです。
禅僧の食事である精進料理も日本料理に影響を与えてきました。
この時代に一汁一菜という質素倹約を重んじた食事のかたちができあがり鎌倉武士の食事の基本となり、後世につづく日本人の食事のかたちができました。
また心地覚心(しんち かくしん)という臨済宗の僧侶が1249年(宝治3年)に宋へ渡り、中国での師 無門慧開から禅公案集『無門関』を得て帰国しました。覚心は国師として中国へ渡ったたいへん高名な僧で、宋の径山寺(きんざんじ)のみそ製法を伝えました。

高校時代の古典の時間で出てきた記憶があります。『徒然草』215段。
執権 北条時頼とその一門である北条宣時が、台所の素焼の器に残っていた少しのみそを肴にして楽しく酒を飲み交わした…という逸話。時の権力者 執権でさえ、みそだけを肴に楽しく酒を飲んだなんて、本当に質素な生活ですね。
『徒然草』215段は こちら。
室町時代

室町時代はみそ汁が庶民の間に浸透しただけでなく、現代に伝わるみそ料理のほとんどがこの時代につくられ始めています。
大豆、稗、粟の栽培奨励策に伴い大豆の生産が増え、みその自家醸造が始まったのもこの時代です。
今では「お行儀悪い!」「ネコまんまか!」と言われそうですが、当時は「武家にては必ず飯わんに汁かけ候」*といわれ、室町から戦国時代にかけてはご飯にみそ汁をかけて食べるのが普通でした。
*『宗五大草紙(そうごおおぞうし)』…1528年(享禄元年)に伊勢貞頼によって記された武家故実の書。武家奉公人としての心得や幕府殿中における諸作法・心がけ、先人の教訓などを25項目281か条にしてまとめたもの。
この頃柚子みそ、鉄火みそ**等の「なめみそ」が現れます。おかずみその登場です。
**鉄火みそ 炒り大豆に刻みごぼう、をゴマ油でいため、赤みそ、砂糖、みりんで練り上げたもの。
室町時代の『大草家料理書』は当時の日本料理の様子を伝えていますが、「汁は古味噌をこくして、能かへらして煮出し後入候…すいくちは柚を入れて吉也」とあります。この料理書は室町幕府の官職につく大草家に伝えられる書なので、少なくともみそ汁が武家では一般的に飲まれていたことがうかがわれます。
史料『大草家料理書』はこちら。
戦国時代

戦で戦闘能力を最も左右するものは何でしょうか。それは兵糧です。「ハラが減っては戦はできぬ」ですね。
戦国武将たちは皆、兵糧に重大な関心を持っていました。特に米とみそは絶対に必要な兵糧でした。
戦陣に向けて携帯でき、かつ日持ちするよう、各武将は工夫を重ねたようで、干したり焼いたりてみそ玉にしたものをほかの食料と一緒に竹の皮や手拭いで包んで腰に下げたり、藁にみそをしみこませて携帯したり、また干し大根などをみそで塩辛く煮詰めて干し固めたものを陣中では水に入れて「戻しみそ汁」のように飲む方法も考え出されました。
戦国武将がどれだけみそを重要視したか…たとえば武田信玄は信濃遠征に備え、農民に大豆の増産を促し、みそづくりを奨励しました。

また伊達政宗は軍用みそを自給しようと考え、城下に「御塩噌蔵」と呼ばれるみそ工場を建てました。
これが日本で最初のみそ工場といわれています。
戦国の世が過ぎて安土桃山時代の千利休の小話ですが、久須見疎安によって記された『茶話指月集』 によれば、千利休が親しい茶人からとっさのおもてなしに柚子みそを出されたと載っています。この小話のオチは、実はとっさはフリだけで、実はしっかり準備されたおもてなしだったと知ってかえってがっかりした、というものですが、茶道と柚子みそ。心が豊かになるもてなしの一つにみそが使われた、と当サイトでは受け取りたいと思います。
史料『茶話指月集』はこちら。
江戸時代

ようやく安定期を迎えた江戸時代、各地から武士のほか人足が集まり江戸は100万人都市に成長します。
江戸の生産だけではみその需要をまかないきれず、家康の出身地である三河の三州みそや仙台みそが海路で江戸に運ばれ、みそやは大繁盛しました。
「みそを買う家には蔵は立たぬ」ということわざがあったように、武士、農民、大商人は自家醸造がほとんどで、みその販売はもっぱら長屋暮らしの庶民を相手にしていたのです。
味噌にまつわることわざはこちら。
江戸や京都大坂での味噌屋の看板、味噌売りの説明が挿絵入りで『守貞謾稿』に記されています。
高級料亭の商いもはじまり、『豆腐百珍』『黒白精味集』『素人庖丁』など数百冊の料理本が刊行されて日本料理はもとより、みそ料理はますます洗練されていきました。
また各藩でも藩内で収穫される作物を使ってみそを醸造するようになり、各地方で特色のあるみそがつくられるようになりました。
江戸時代の料理書『料理物語』(1643年(寛永20年)の九 汁の部には46種の汁物の調理法が載っていますが、鯛のふぐ擬き、すずきの汁、鯉の胃煎り汁、鮒の汁…とみそ仕立ての汁の調理法が続きます。
史料『料理物語』九 汁の部 の内容はこちら。

このように庶民にもみそは不可欠のものとなり、みそを題材とした落語や川柳もたくさん作られました。
味噌にまつわる落語はこちら。

古典落語の「味噌蔵」や「みそ豆」はタイトルにも出ていますが、「馬の田楽」「黄金餅」などなど、みそがなにかと噺に出てきます。
You Tubeでも見られるものがありますよ。