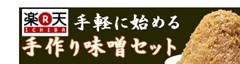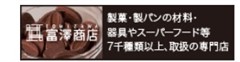落語「二番煎じ」

「二番煎じ」あらすじ
江戸の名物に火事が入っているように、毎晩のように半鐘が鳴っていました。お上も「いろは四十八組」をこしらえたり、各町内でも火の番小屋を置いて、自費でもって火の廻りを雇ったとか。雇われるのは血気盛んな若者というわけではなく道楽者のお年寄りたちが多かったようです。
ある寒い晩、夜廻りで番小屋に集まったところで、大勢でぞろぞろと廻るよりは二組に分けて廻りましょう。一の組が廻っている間はニの組は休んでて、一の組が戻ってきたらニの組が廻りに出る、となりました。一の組が夜廻りしながら愚痴やら世間話やら話しながら、音を鳴らして廻るはずなのに寒くて懐から手が出ない、金具が冷たくてつかめない。「火の用心」の掛け声を出すにも昔時分の話をしながら、ようやく一廻りして番小屋に戻りました。
「あァ、そこピタッと閉めてピタッと、ね。隙間っ風が入るってえと寒いから。おい、あの惣助さん 、炭箱取っとくれ。こればっかりの火じゃね、暖まりゃしない。あたしたちが帰ってくんのわかってんだからねえ、ニの組のほうでこういうところ…、いやーア、あの寒さてえのはなかったですねえ。鼻でも耳でもね、ほら、まるでね、こっちが氷みてえンなっちゃったン。うゥーん、一の組のほうへね、お誘いしてね、すいませんでした。いや、当初あたしね、一の組の方が先にお役御免になって、これァ得だな、楽だなと思ったン。ところがね、一の組はね、ろくに暖まってないうちにスーッといきなり出ちゃうでしょ? これァニの組のほうが得でしたな」
「ええ、月番さん」
「なんです、先生」
「実は…出がけに、娘が、おとっつぁんは寒い中、火の廻りで歩くんだから…、風邪をひいてはいけない。これを持ってって飲んだらどうだと…瓢に酒を入れてもたしてくれましたのでな、これを一つ、皆さんで飲むというのは…どういうもんでございましょう」
月番さん、「そういうことをされちゃ、困るんですよっ!」と怒りながらも土瓶を持ってこさせて酒を移し、火に載せます。一同、理解に苦しみ、「…お燗をつけて、どうなさる」
「あんたもわかんないねえ、冷で飲んじゃあ毒だからお燗をして飲むんですよ!」
「だってあァた、飲んじゃいけないって」
「そりゃそうですッ。瓢箪から出るお酒飲んでちゃ、まずいでしょう。土瓶から出る煎じ薬だったら、どうってェことはないン…」
「ええ、月番さん」
「なんだい惣助さん」
「えー、あたくしね…、みなさんがそういうものをお持ちになるんじゃないかと思いまして、…あたくし、これ持ってまいりました」
といって懐から取り出したのは猪の肉。実は背中に鍋も背負っていました。
「偉い人だねーえ…。そういやなんか猫背だなとは思っていたんだ。鍋が入ってたの、ええ?」
そうして番小屋で熱燗と猪鍋は始まりました。一本しかない箸を回しっこしながらふぅふぅ言って食べ、酔っぱらい都都逸まで始まります。
「(表から)番ッ!」
「(酔ったまま)今、なんか言ったろ?」
「言いませんよぉ」
「番ッ!」
「あ、表。ええ? あのね、蒲鉾屋のあの、アカ。犬。あれがね、あの、匂いを嗅ぎつけてね、一書に食いてえってんで来たんだよ、うん」
「番ッ!」
「シッ」
「番、番ッ!」
「シッ、シッ」
「(表の声、厳しく)これッ、番の者はおらんのか!」
「(震えあがって声をひそめ)おゥい、大変だ! …おい……、あの、犬じゃない、お役人!」
慌てて火傷を死ながら鍋や土瓶やらを隠しますが、お役人の問いただされます。
「は……今夜より、…ふた、二組に分かれて廻っておりまして一廻りして、ただいま…、ここで休んでおりますところ…。他の組が…廻っております」
「…今、拙者が入ってまいった折に、なにか土瓶のようなものをしまったな、あれは何だ」
「…風邪をひくといけないから、薬を煎じて飲もうと…、薬を煎じておりました」
「うぬ。拙者が『番』と申したら『シッ』、『番、番』と申したら『シッシッ』と申した。あれはなんだ」
「…寒いから火(し)をどんどん起こそう、火だ火だ、火、火、とこう申したん…」
「うむ。風邪藥か。よし、ちょうどよい。拙者も両三日前より風邪をひいておる。拙者にも一杯もらいたい」
お役人、出された煎じ薬をぐいっと一飲みし、舌鼓を打ちながら
「(低い声で)そのほうたちはこれを飲んでおったのか」
「(覚悟をして低い声で)さいでございます」
「間違いなく、これを飲んでおったかッ!!」
「(身が縮むように)さいでございます」
「…(ニンマリ)よい煎じ薬じゃ。(さらに飲んで)ウーッ。いま一杯もらいたい」
「あーあ、そうですかぁ。(ホッとし、みんなに小声で)よかったよォ、これで同罪だよ」
「うむ。アーッ、体が暖まってなによりだ。これ、表戸を閉めよ。棒を支えッ。…鍋のようなものをしまたな?」
「は…あ…。煎じ薬の口直しを…煮ておりました」
「おーお、さようか。拙者もほしい。これへ出せ」
「えエ、おそれいりますが、煎じ藥がきれましてございます」
「なに、煎じ藥がないか?」
「はい。一滴もございません」
「うむ、しからば拙者、いま一廻りしてまいる。その間に、二番を煎じておけ」
ここでは味噌がテーマなので上記はだいぶ削ったあらずじで、猪鍋が味噌仕立てだった、くらいしか言えないのですが、一の組が廻っている時の旦那方の世間話や、猪の肉を持ってきた惣助さん(他の書では宗助さん)がお役人への言い訳にスケープゴートに名前を出されるとか、日本人社会の習性がちりばめられていて、あらすじに端折るのがもったいない噺です。
ほかの噺家さんの「二番煎じ」では、猪鍋の味付けは味噌とは伝えていないものもあるようです。とはいえ、冷え込む夜の番小屋で始まった味噌仕立てのあったかい猪鍋なら、その香りは外にも漏れ出していたはず。
月番さんもお役人も、一応諫めておきながら「土瓶にいれた煎じ薬なら」「煎じ薬ならわしにも」と乗っかってしまうところがよき時代の懐の深さ、なのかもしれません。
熱燗でよっぱらったり猪鍋を食らう夜廻りたちを志ん朝が演じたら、さぞ名演だっただろうな、と思える一番です。