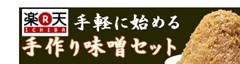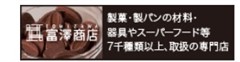落語「味噌漉し」

小説家で推理作家の結城昌治(1927〜1996年)氏の残した落語噺がありますので紹介させていただきます。
「味噌漉し」あらすじ
モテる男は粋な男。
べっ甲問屋山崎屋の若旦那はからきし女にモテないが、世間にはモテるように見せたがる。長唄、常磐津、小唄など片っ端から習ってモテ男になろうとするが筋が悪くて三日坊主。惚れあった印に見せようと女の名前を片っ端から体に彫ったり、花魁に五十両の大金を払って演技口上を言わせるが、ことごとく周りには相手にされず当人が仕組んだものとバレている。けれどもどうにか色男の評判をワッと立たせたい。
挙句の果てに、勘当されたい、と親に申し出るが親は勘当する気はさらさらない。ようやく仕送りを受けながら勘当の体裁をつくり、芸者と心中を企ててて川に飛び込もうと向かう途中に追い剥ぎに遭う。そもそも死ぬ気は毛頭なく、心中の手前でやめようと思っていたから命乞いをしてふんどし一丁で実家へ戻った。
「もうこりごりです」「一緒にいた女はどうした」「あれ、おとっつぁん知ってるんですか」「あの追い剥ぎは私と番頭の佐兵衛だ」「ようやくわかりました。心を入れ替えて何でもやらせていただきます」「それじゃ味噌漉しでも何でもやるか」「いえ、味噌漉しは勘弁してください。またこし(腰)が抜けるといけません」。
山東京伝(1761〜1816年)の『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』を種本とした「落語 味噌漉し」は、『別冊小説新潮』1975年(昭和50年)秋号掲載。結城氏の小説集『噛む女』に収められています。
山東京伝の「江戸生艶気樺焼」(1785年 蔦屋重三郎から板行)は、黄表紙最盛期の代表的作品です。
大金持ちの息子 仇気屋艶二郎(あだきや えんじろう)は抜け上がった額、あぐらをかいた鼻、広がった顎の醜男ですがうぬぼれが強く、自分は女性にもてるはずだと確信していて、浮名を流したいと金を使って噂づくりをするが世間は相手にしない。心中まで企てて家に戻りますが、浮名を流したい男のあっけらかんとした反省のなさと、金のために心中芝居につきあった女の無表情さが対照的に際立っています。