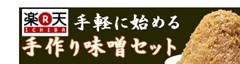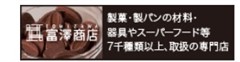『春情蛸の足』 田辺聖子
作家 田辺聖子氏(1928年〜)の1987年に単行本として刊行された短編集。
本書には8編収められていますが、全編において大阪ならではの豊かな食を巡る男と女のやりとりが描かれています。決して豪勢な高級料理ではなく、たこやき、お好み焼き、すき焼きといった庶民の味。胃袋をつかんで離さない、また食べたくなる好みの味。
「味噌と同情」の中垣は40代の勤め人。中途入社だから出世の道もなく日々仕事を適当にこなしている。
妻 邦子は仕事では英語も駆使するキャリアウーマン。料理に味噌は使わない。だから家に味噌も置いていない。料理は週末に作りだめして冷凍している。
「お常」の常子は、典型的な大阪顔でどっしりといかつい43歳のおばさんだが、中垣はお常の料理で懐かしい味噌の味に目覚めてしまう。
そのうち、白味噌で煮たすじ肉のドテ焼きまで出て来た。こんにゃくとともに、白味噌の中でぐつぐつと煮られ、とろけるばかり柔らかくなっている。
それよりも中垣をほろりとさせたのは、その白味噌(これには赤味噌も混っていたようであるが)の味である。
(うーむ、長いこと味噌ちゅうもん、食わなんだ!)
里心がついてしまったのだ。
中垣はお常に通ううち、「お常」がなかったら「どないして生きていってええやら、わからへん」と常子に言うほどに。
古い、昔ながらの浪花の味をお常では食べさせてくれる。
味噌のいい匂いがたちこめ、中垣は幸福の予感にしびれる。
「これ、本当は、丸餅なんですけど、いまはもう切り餅しかないんでごめんなさい。具の駄大根やにんじんも、雑煮大根いう、細いのを丸のまま切るのやけど、お正月過ぎたら売ってないから、大きいのを銀杏に切ってますよ、ごめんなさい」
「結構、結構」
中垣は敬虔に受け取る。春先に白味噌雑煮というのは妙だが、雑炊代わりと思えばいい。
ともかくお汁を吸う。
まったりと重厚だが、舌から咽喉へ、吸いこまれやすい味である。白味噌に、ほんの少し隠し味風に赤味噌が入っているにちがいない。とろりとろとろとした味噌汁である。
常子の分かれた亭主が "英語遣い" だからか、こうした料理をつくる常子に自分と重ね合せて "英語遣わず" 同士の連帯感なのか同情なのか、決して色恋ではないが、しかしうまい料理にうっとりとした気持に浸る。
8編すべて目の前で見ているような錯覚に陥るほど、食の表現が豊かです。
大阪弁なのも良い具合に力が抜けて読んでいて楽です。
「たこやき多情」では、
中年の無口なおばはんがいて、皿におでんと、ドテ焼きをとってくれる。ドテ焼きの串をくわえ、白味噌が垂れないように、唇でしごきながら中矢はすじ肉を食べる。びっくりするくらい柔らかく煮込んである。白味噌のはんなりした甘味が何ともいえない。
ここでも白味噌のドテ焼き。
すじ肉は関西ではよく食べるようですね。
また「人情すきやき●」では、東京出身の妻 令子が鶴治に言う台詞
東京人と関西人では味つけが違う。すき焼きもしかり。教えようとしても教えられない鶴治は、元彼女を誘い出してすき焼き屋へ時々行くようになります。
「お好み焼き無情」では、妻は大阪育ちでも義母が大阪ではないと食生活が影響される様が描かれています。
妻がすると娘もやる。女系家族だからどうしようもない。
吉沢が見ていると、さながら猫のエサである。
(中略)
いつか、それについておずおずと批評したことがあった。味噌汁は味噌汁、めしはめしとして食べたほうが、見た目も美的ではあるまいかという、遠慮がちな感想である。
妻と義母はたちまち反論した。
吉沢にとっては、味噌汁を飯にぶっかけるのは乞食飯で、うどんの黄金色の汁の中にぱらぱらと入れる白い冷や飯は霞の中からほの見ゆる桜の花。文化の程度が違うそうです。
主人公の男や夫がどうしてこう弱い者として描かれているのか、はたまた妻へのあきらめか。妻に強いることなく別の道で食の欲求を満たそうとする男たちが、なんとも哀しくもおかしく描かれています。
田辺聖子氏は大阪で生まれ育ったので、関東の味は絶対だったのかもしれません。
上京しても妻が東京人でも、関西の味、故郷の味は忘れがたい。やっぱり慣れ親しんだ味の美味い料理は、至福の時間をもたらすことが男性の目線で描かれています。