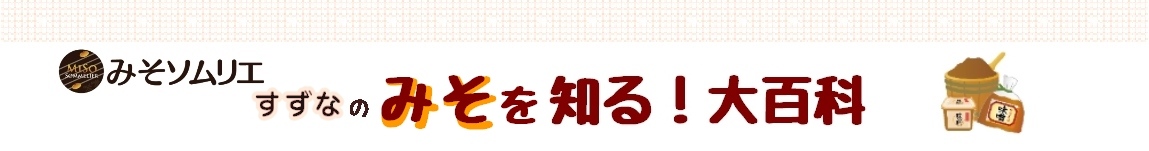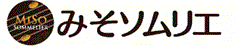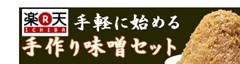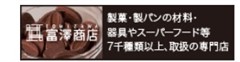みその定義
みそはご存知の通り食品であり、調味料ですが、消費者庁告示のみそ品質表示基準第2条(平成23年10月31日)によって定義されています。
以下原文です。
みそ
次に掲げるものであって、半固体状のものをいう。
1 大豆若しくは大豆及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに、米、麦等の穀類を蒸 煮してこうじ菌を培養したものを加えたもの又は大豆を蒸煮してこうじ菌を培養 したもの若しくはこれに米、麦等の穀類を蒸煮したものを加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させたもの
2 1に砂糖類(砂糖、糖みつ及び糖類をいう。)、風味原料(かつおぶし、煮干 魚類、こんぶ等の粉末又は抽出濃縮物、魚 醤 油、たん白加水分解物、酵母エキ じよう スその他これらに類する食品をいう。以下同じ。)等を加えたもの 米みそ みそのうち、大豆(脱脂加工大豆を除く。以下同じ。)を蒸煮したものに、米を蒸 煮してこうじ菌を培養したもの(以下「米こうじ」という。)を加えたものに食塩 を混合したものをいう。
定義としてみその形状と、1、2で製造方法と原材料について書かれていますね。
簡単にいうと、半固体状のもので、
- 大豆、米、麦等の穀類を蒸煮し、米麹、麦麹に食塩を混ぜて発酵・熟成させたもの。
- 1に砂糖類、風味原料(かつおぶし、煮干魚類、こんぶ等の粉末または抽出濃縮物、魚醤油、たん白加水分解物、酵母エキス類)等を加えたもの 。
です。
原料 大豆
みその大豆は、丸大豆を使用します。
上記の定義をさらりと読むと、原料は大豆なので当たり前と思ってしまうのですが、この大豆は丸大豆です。
しょうゆの品質表示基準と比べるとわかるのですが、しょうゆの定義として原料の大豆は「脱脂加工大豆を含む」と明記されています。みその品質表示基準にはそのような記述はありません。
みそは丸大豆を使用します。
丸大豆とは
 丸大豆という品種があるように思えてしまいますが、「大豆まるごと」ととらえればよいと思います。丸大豆しょうゆと銘打ったしょうゆがありますが、あえて丸大豆を出しているのは、大規模工場生産のしょうゆをはじめ流通しているしょうゆの約80%が脱脂加工大豆を使用しているからです。「丸大豆」とすることでおいしさや贅沢感が出て価格にも反映されています。
丸大豆という品種があるように思えてしまいますが、「大豆まるごと」ととらえればよいと思います。丸大豆しょうゆと銘打ったしょうゆがありますが、あえて丸大豆を出しているのは、大規模工場生産のしょうゆをはじめ流通しているしょうゆの約80%が脱脂加工大豆を使用しているからです。「丸大豆」とすることでおいしさや贅沢感が出て価格にも反映されています。
大豆から大豆油を搾取したあとの脱脂された大豆を脱脂加工大豆、もしくは脱脂大豆といい、大豆油はオレイン酸、リノール酸などからなるので食用もしくは工業用に使われます。
第二次世界大戦前後の物資の足りない頃に大豆から油脂を取り、その大豆かすを利用したことから脱脂加工大豆のしょうゆが生まれました。
原料 麹菌
みその発酵には麹菌を使います。
みそは発酵食品ですが、発酵といってもいろいろな発酵があります。関わる菌も、酢の酢酸菌、納豆の納豆菌、ヨーグルトでおなじみの乳酸菌やビフィズス菌などなど。
また発酵と思うと、酵素や酵母を入れる・使うと思いますが、定義としては麹菌のみです。
実際、麹菌発酵によって、結果として酵素が生まれ、酵母も育ちます。またあえて特定の酵母を使っていると銘打っているみそもありますが、定義としては、麹菌を培養した米麹、麦麹、豆麹を使用するのみで、酵素や酵母についてはありません。
砂糖類 と だし
項目2については、いわゆるだし入りみそのことです。

平成12年(2000年)にみそ品質表示基準が定められましたが、当初はこの項目はありませんでした。しかし、調理の簡易化でだし入りみそが多くなり一般的になったことで平成23年(2011年)10月の改正告示で、だし入りみそもみその定義に入れられました。
関西白みそなど、水あめや砂糖類を入れるものも項目2に当てはまります。
以上がみその定義です。
でも色や味での分類もあります。どんな種類があるかは、みその種類 3つの分け方へ