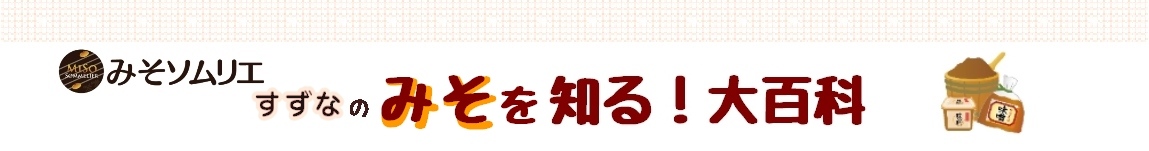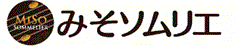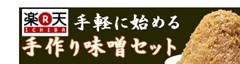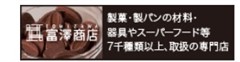秋田みそ
|
秋田県 |
秋田みそは秋田県でつくられるみそです。
秋田みその特徴
色は赤系〜淡色系の間で数種類あります。
米みそで辛口の粒みそです。
米どころなので米麹の割合が多く、塩分も徐々に低く甘口化傾向にあるようです。
開封した時の香りは、米麹の甘い香りが目立ち、なめてみても甘味を感じます。麹歩合が高いのだな、と思えます。
近年の開発としては、秋田香酵母 ゆららが大きな特徴です。
秋田県味噌醤油工業協同組合と秋田県醸造試験場(現 秋田県総合食品研究所)が4年がかりで共同開発した 秋田香酵母 ゆらら は、秋田県で初めて開発されたみそ用酵母です。

秋田香酵母・ゆららをつかった秋田みそにはロゴマークが付されており、その特徴は下記3つが挙げられます。
- ふわっと広がる“華やかな香り”
- 飽きのこない“さわやかな味”
- 光沢と照りのある色鮮やかさ
また、ゆららのほかに原料には秋田県産大豆 リュウホウ、米麹には県産米 あきたこまちと県産麹菌AOK139、県産乳酸菌AL-1 など、おいしくて安心安全な秋田みそを全国に届けようと県内総バックアップ体制で研究されています。
秋田みその歴史

秋田は米どころと知られるように麹の原料である米、そして大豆が豊富に収穫されたため、江戸時代には農家だけでなく武家や町家でも各家庭でみそが作られていました。
佐竹氏による久保田藩(秋田藩)の財源は当初は院内銀山、阿仁銅山などの鉱山のほか材木に使われる秋田杉(林業)を主力としましたが、もう一つは米でした。
17世紀を通じて秋田のみそは、玉味噌と呼ばれる自家製のみそがほとんどでしたが、19世紀の天保の大飢饉の際にはみそが高騰したという記録もあることから商品として流通していたことがうかがわれます。
明治時代になるとみそやしょうゆを工場で生産する企業が誕生し、1910年には小玉合名会社が初めて「秋田味噌」という名称を使用しました。
 秋田県内の多くの家庭では、1940年頃まで自家製のみそと副産物の溜り(たまり)で自給自足しており、購入するのは盆正月など特別な行事の時に限られていたようです。
秋田県内の多くの家庭では、1940年頃まで自家製のみそと副産物の溜り(たまり)で自給自足しており、購入するのは盆正月など特別な行事の時に限られていたようです。
みそを使った秋田県の郷土料理 ご当地料理
- 石焼き鍋
- いものこ汁
- マタギ鍋
秋田みその製造元 製造メーカー
【秋田市】
- 貝沼商店
- (有)仙葉善治商店
- 大彦商店
- 森九商店
- 那覇商店・山蕗
- 土田商店
【由利本荘市】
- (有)マルイチしょうゆみそ醸造元
- ヤマキチ味噌醤油醸造元
【にかほ市】
【大仙市】
- 東北醤油(株)
- 旭醤油味噌醸造元
- 伊富味噌醤油店
- 小松糀屋
- 須田麹店
- 黒澤糀屋
【仙北市】
【美郷町】
- 照井味噌醤油醸造元
【横手市】
- (有)新山食品加工場
- (名)内藤醤油店
- 畑良商店
- 麹屋近野商店
【湯沢市】
【潟上市】
【五条目町】
- 坂市商店
【男鹿市】
- 秋田みなみ農業協同組合
- (株)諸井醸造
【能代市】
- (名)西村醸造店
- 山下醸造店
- 原田醸造店
【鹿角市】
- 能勢醸造(資)
- (株)浅利佐助商店
【大館市】
- (有)佐々木こうじ店
>これぞおふくろの味 全国の郷土みそ に戻る