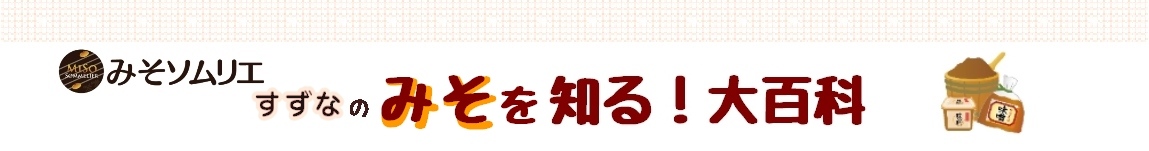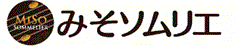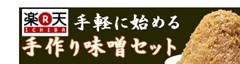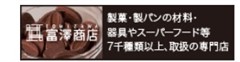津軽みそ
|
青森県 |
青森県津軽地方のみそをいいます。
津軽みその特徴
赤色の中辛〜辛口の米みそです。
津軽地方の寒冷な気候から熟成には長い期間を必要とし津軽三年味噌とも呼ばれるほど長期間を要します。
その間の酸敗を防ぐために塩分濃度は13%前後と高めに設定されていますが長期間の熟成によって十分に塩かどがとれ、独特のうま味があります。みそは魚の臭みを消す働きをするので、郷土料理のじゃっぱ汁や貝焼き味噌などにも用いられます。
津軽地方は大豆の生産地で、特に鶴の子という品種はみそづくりに適しています。
津軽みその歴史
 江戸期に入って近江や越前から来た商人たちが津軽の各地で糀屋を開きました。
江戸期に入って近江や越前から来た商人たちが津軽の各地で糀屋を開きました。
1624年(寛永元年)に青森港が開港されると、蝦夷地や下北地方へ出荷する酒の製造が弘前藩でも始まり、それに伴ってみそや醤油の商業的な製造も行われたと考えられています。
1648年(慶安元年)の津軽藩律では、御用達商人の味噌の配合は「大豆1升に対して麹6合、塩5号」と定められており、当時から米麹が使われていました。
また弘前藩は平時から軍需備蓄のために多数の麹屋(室屋)に営業を許可し、みそづくりを奨励していました。
 1671年(寛文11年)の税金にする記録から、この頃までには南部地方の大豆を原料として商業的なみそづくり行われていたことが読み取れます。
1671年(寛文11年)の税金にする記録から、この頃までには南部地方の大豆を原料として商業的なみそづくり行われていたことが読み取れます。
1703年(元禄15年)にはみそが蝦夷地(北海道)に盛んに出荷されるまでに成長し、技術や気候の問題からみそを生産できなかった蝦夷地の需要を満たす役割を担っていました。
そうして出荷された蝦夷地において「津軽みそ」という呼称が生まれた可能性が指摘されています。
現在でも津軽のみそは北海道でも消費されているそうです。
みそを使った津軽、青森の郷土料理 ご当地料理
- イカの鉄砲焼き
- じゃっぱ汁
- そばっかけ
- みそチャップ
- 八戸せんべい汁
- 貝焼みそ
津軽みそ 青森県の製造元 製造メーカー
- (株)中村醸造元
- (有)横山醸造
- 大澤醸造(株)
- さいした商店醸造
- (株)小野寺醸造元
- 佐国屋
- 加藤味噌醤油醸造元
- 斎藤醤油醸造元
- 古川味噌醤油醸造元
- コムラ醸造(株)
- (有)北澤商店
- カネショウ(株)
- 鹿内味噌醤油工場
- 野坂味噌醤油店
- (名)高村醤油本店
- 加藤こうじ店
- (有)P&Dカワムラ
- 津軽味噌醤油(株)
- (名)宝醤油店
- 甲文醤油(名)
- 上北農産加工(農協)
>これぞおふくろの味 全国の郷土みそ に戻る