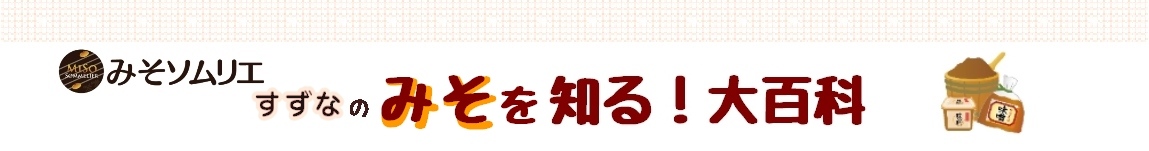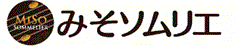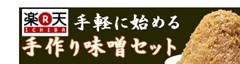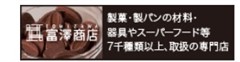越後みそ
|
新潟県
|
越後みそは新潟県の旧 越後国地域ででつくられるみそです。
越後みその特徴
赤色系の米みそで辛口です。
精白した丸米を使っているため、特に上越地方のものは米粒がみその中で浮いているように見え、浮麹みそ(うきこうじみそ)とも呼ばれます。
蒸煮した大豆を冷却せずに食塩と混ぜて濾し網で粉砕し、製麹後に塩切りを行わずに温度を下げて余分な水分を飛ばす事により、麹の抜け殻が生じて「浮麹」が得られます。
浮麹は、麹菌の菌糸が米粒の組織と絡まって袋状になったもので、みそ10gあたり40個ほどの麹の完全粒があると目視で十分に確認できます。
上越地方では大豆:米麹が10:9〜1:1と麹の比率が高く、赤みも薄くしていたため、麹がよりはっきりと浮いて見える傾向がありました。
明治時代にはこの比率が5:6となる場合もあり、黄金みそと呼ばれていたそうです。
新潟市など下越地方では大豆と米麹の比率が10:7程度という時期もあり、鮮やかな赤色が特徴的でした。
越後みその歴史

永禄7年(1564年)に関東地方に出兵した上杉謙信が野田地方(現在の千葉県野田市)でみそづくりの技術を兵に習得させ、これが本拠地の越後国に広まったという伝承があります。
農家で自家消費用にみそが製造されていたいましたが、軍事用食糧を準備するため城下町でみそづくりが進められ、村上藩や新発田藩などでも製造販売が行われていました。
明治時代になるとカムチャツカ半島や千島列島、北海道などへ北洋漁業や移住者向けの食料として出荷され、これが1944年頃まで続いていました。
また、関東大震災後には関東地方へ出荷が始まりました。

みそを使った越後新潟の郷土料理 ご当地料理
- しょっから煮
- けんさん焼
- ワッパ煮 粟島浦村
- たら汁 糸魚川市
- 大葉みそ
- 青唐辛子みそ
- のっぺい汁(醤油、みそ
- あんこう汁
- あんこう鍋
- すけとの沖汁 佐渡
- 沖汁
越後みその製造元 製造メーカー
>これぞおふくろの味 全国の郷土みそ に戻る